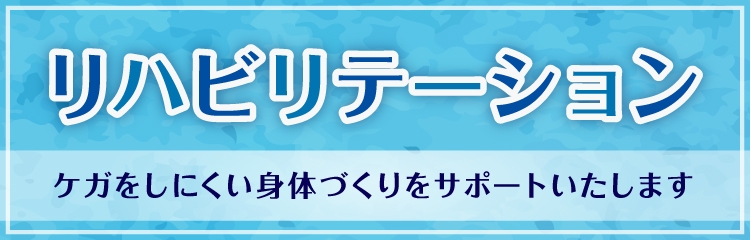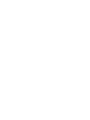肩の痛み
X線で骨や関節には異常がないのに痛くて関節が動かせなくなる肩関節周囲炎(いわゆる四十肩五十肩)という疾患があります。これもベースには筋肉の老化があるのですが、ここに起こった炎症が拘縮(筋肉が硬くなって動かせなくなった状態)を引き起こし、どんどん悪くなっていきます。治療はお薬や物療、ヒアルロン酸注射、理学療法士によるリハビリ等を行います。また簡単に四十肩で片付けられている患者さんの中にかなりの頻度で腱板損傷などの病態が隠れていることがありますので要注意です。 他にも石灰(カルシウムの結晶) 沈着や腱鞘炎で激しい痛みが出る事もあります。
肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)
原因・病態
五十肩とは40~60歳代に多く見られる、特定の原因がなく肩関節に持続的な疼痛と自動・他動可動域の著しい低下を伴う状態です。古くは50歳代を中心とした年代にしばしばみられる肩関節の痛みと運動制限を主な症状とする症候群を「五十肩」と呼んでいましたが、医療の進歩に伴い、こうした中に腱板断裂や石灰性腱炎などの疾患が含まれることが明らかになったため、現在ではこれらの疾患を除いたものを肩関節周囲炎あるいは五十肩(狭義の五十肩)と呼ぶようになりました。病態としては肩甲上腕関節や肩峰下滑液包(けんぽうかかつえきほう)の炎症、癒着によって疼痛、可動域制限を生じるとされていますが、その詳しい原因は分かっていません。
症状
肩関節痛や可動域制限のほかに肩甲部から上腕や肘への放散痛もしばしばみられます。疼痛が強い時期には安静時痛や夜間痛を伴うこともあります。また、可動域は自動・他動運動の両方が全方向に制限され、この点が腱板断裂とは異なります。
検査・診断
問診、診察によって肩関節の疼痛部位、関節可動域制限を評価し、診断します。
検査ではX線(レントゲン)検査や肩関節MRIを施行し腱板断裂や石灰沈着性腱炎、変形性関節症などの除外を行います。また、頚椎症性神経根症でも肩周囲に疼痛を来すことがあるので、疑わしい場合は頚椎レントゲンや頚椎MRIを行うこともあります。
検査ではX線(レントゲン)検査や肩関節MRIを施行し腱板断裂や石灰沈着性腱炎、変形性関節症などの除外を行います。また、頚椎症性神経根症でも肩周囲に疼痛を来すことがあるので、疑わしい場合は頚椎レントゲンや頚椎MRIを行うこともあります。
治療
自然経過で治ることもありますが、放置すると関節拘縮が進行し日常生活が不自由になるばかりでなく、可動域を取り戻すまでに時間がかかるようになります。
まずは消炎鎮痛薬など内服治療や注射加療、リハビリテーションを行います。治療に半年~1年、場合によっては2年近く要することもありますが、多くの場合は改善し、予後は比較的良好です。
まずは消炎鎮痛薬など内服治療や注射加療、リハビリテーションを行います。治療に半年~1年、場合によっては2年近く要することもありますが、多くの場合は改善し、予後は比較的良好です。
当院での診療内容
当院では消炎鎮痛薬などの内服加療にステロイドやヒアルロン酸を用いた注射療法、理学療法士によるストレッチ、モビライゼーション、可動域訓練などの理学療法、低周波やホットパックなどの物理療法を組み合わせて治療を行います。特に初期の夜間痛が強い時期は関節内の炎症が強いため内服治療のみでは疼痛コントロールが難しくステロイド注射が奏功することが多いです。また、安静時痛や夜間痛が落ち着いた後も関節拘縮が残存することが多く、当院では理学療法を積極的に行っております。
腱板断裂
原因・病態
腱板は肩関節を支えるインナーマッスルであり、棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋の4つの筋肉から構成されます。この腱板が上腕骨付着部から剥がれたり、損傷した状態が腱板断裂です。原因としては加齢や使い過ぎにより傷んだ腱板に外傷などの外的要因が加わることにより発症すると考えられていますが、はっきりとした外傷によるものは半数程度で、残りは日常生活動作レベルの負荷で発症します。また、糖尿病や高血圧症、高脂血症などの生活習慣病、関節リウマチや喫煙は腱板断裂の危険因子といわれています。
症状
肩関節痛や可動域制限、夜間痛といった四十肩・五十肩と似たような症状を認めますが、四十肩・五十肩と比べ可動域制限が少なく、途中で痛い角度があるもののある程度は上げ下げができることが特徴です。断裂範囲が大きくなると痛みよりも麻痺のように力が入らなくなることにより挙上が困難となります。
検査・診断
問診、診察で腱板のうちのどの筋肉がどれほど損傷しているのかを推測することができます。
検査では、MRI検査は腱板の断裂部位、程度、腱板の脂肪変性の評価などが可能であり大変有用です。X線(レントゲン)検査でも進行した断裂では上腕骨頭の上方化や大結節部の変形(骨硬化、大腿骨頭化)を認めることがあります。
検査では、MRI検査は腱板の断裂部位、程度、腱板の脂肪変性の評価などが可能であり大変有用です。X線(レントゲン)検査でも進行した断裂では上腕骨頭の上方化や大結節部の変形(骨硬化、大腿骨頭化)を認めることがあります。
治療
損傷した腱板が元通りに修復されることはありませんが、安静、消炎鎮痛薬などの内服加療、注射加療、リハビリテーションを行うことで7割ほどは軽快します。特にリハビリテーションで残っている腱板の機能を賦活化させることは重要です。
保存加療に抵抗性の方やスポーツ愛好など活動性の高い方は積極的に手術治療が選択されます。
保存加療に抵抗性の方やスポーツ愛好など活動性の高い方は積極的に手術治療が選択されます。
当院での診療内容
当院では診察、X線検査、MRI検査で腱板の状態を評価し、投薬加療、注射加療、リハビリテーションを行います。特にリハビリテーションで肩の可動域訓練、残存した腱板の筋力訓練など機能訓練を積極的に行っています。可動域制限や筋力低下が残存する場合もありますが、アスリートのような高パフォーマンスが必要とされる場合を除いて、日常生活や趣味レベルの活動にはそれほど支障を残さなくなる場合が多いです。手術加療の適応の場合は肩関節専門医在籍の病院へ紹介しております。