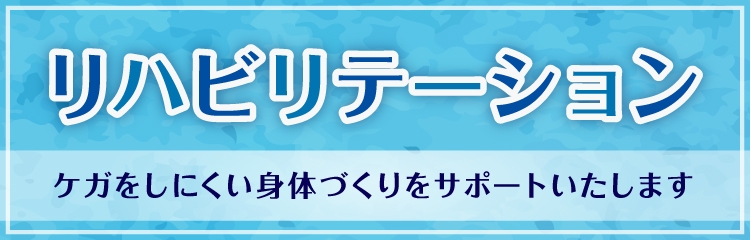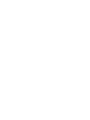肩のこり・首の痛み
肩こりや首の痛みは、頚椎症や、頚椎椎間板ヘルニアなど首や軟骨の変性によって起こる場合もあります。また、外傷やストレス、緊張、姿勢などの要因も考えられます。長引く、何度も繰り返す場合は一度受診されることをおすすめします。最近ではスマホやパソコンを長時間見続けることで首の骨がまっすぐの状態になってしまった「スマホ首」と呼ばれる症状の患者さんも多く見られるようになりました。ストレートネックという症状の1つで筋・筋膜性疼痛が多いとされます。不自然な姿勢が続くと体に様々な不調を引き起こすことにもつながりかねません。医師や理学療法士による正しい指導のもとにストレッチや運動を行なう、猫背にならないように姿勢に気をつけるなどで、日常生活での予防や症状改善が可能です。
頚肩腕症候群
原因・病態
広義には頸~肩~上肢にかけて痛みやしびれなど感覚異常を伴う疾患群の総称であり、競技には椎間板ヘルニアや頚椎症などがみられない、原因不明のものとされます。また、中でも仕事などでの作業が主な原因と考えられる場合は頚肩腕障害とも呼ばれます。
症状
頸や、肩回り、背中、上肢にかけての痛みやしびれ、重怠さ、筋肉のこわばり、頸の可動域制限などが挙げられます。時には手先にかけてのしびれのような末梢神経障害や倦怠感のような自律神経障害、不眠など抑うつ症状が生じることがあります。
検査・診断
問診、診察で疼痛、しびれの部位や程度、生活環境や仕事での作業との関連について確認します。
検査では、X線(レントゲン)検査やMRI検査で変形性頚椎症や椎間板ヘルニアなど他の原因となるような疾患がないか確認します。
検査では、X線(レントゲン)検査やMRI検査で変形性頚椎症や椎間板ヘルニアなど他の原因となるような疾患がないか確認します。
治療
消炎鎮痛薬や筋弛緩薬、末梢神経改善薬などの薬物療法やマッサージ、ストレッチなどの理学療法、温熱療法、低周波など物理療法などが行われます。
当院での診療内容
当院では薬物療法や、理学療法、物理療法などのリハビリテーションを主に行っております。疼痛が強い場合は局所に注射療法を行う場合もあります。治療の主体はリハビリテーションであり、ストレッチ、マッサージに加え、仕事、日常生活での姿勢指導や健康体周囲筋の筋力訓練などご自身でのホームリハ指導も行っております。
頚部神経根症
原因・病態
脊髄が左右に枝分かれした細い神経のことを神経根と呼びます。頸の神経根は左右に枝分かれした後に椎間孔と呼ばれる骨の隙間を通って末梢絵と伸びていきますが、この椎間孔部で神経が狭窄することで痛み、しびれといった症状が生じた状態を神経根症と呼びます。原因はほとんどが椎間板ヘルニアか頚椎が変形してできた骨棘(頚椎症)が椎間孔を狭窄することで発症します。
症状
首から肩、腕、手指にかけての痛み、しびれが主な症状です。症状が強ければ筋力低下を伴う場合もあります。頚椎を後方にそらすことで症状が強くなることが特徴的です。
検査・診断
問診、診察で疼痛やしびれの範囲、症状を誘発する動作姿勢を確認し、おおよその狭窄部位が推測されます。
検査では、X線(レントゲン)検査で頚椎の変形所見を確認します。変形所見には椎間板の扁平化(椎間板腔狭小化)、椎体の変形(骨棘形成)、椎体の前後のずれ(辷り)などが挙げられます。斜めから撮影することで(斜位像)骨棘による椎間孔狭窄の程度を評価することができます。さらにMRI検査を行うことで椎間板ヘルニアの有無を詳しく評価することが可能です。
検査では、X線(レントゲン)検査で頚椎の変形所見を確認します。変形所見には椎間板の扁平化(椎間板腔狭小化)、椎体の変形(骨棘形成)、椎体の前後のずれ(辷り)などが挙げられます。斜めから撮影することで(斜位像)骨棘による椎間孔狭窄の程度を評価することができます。さらにMRI検査を行うことで椎間板ヘルニアの有無を詳しく評価することが可能です。
治療
保存的治療(安静療養、鎮痛薬などの薬物治療、牽引などの物理療法、理学療法、注射療法など)が基本です。しかし、保存的治療でも疼痛が改善しない場合は手術の適応となります。
当院での診療内容
当院ではまず消炎鎮痛薬や神経痛に対する内服薬の処方、頚椎牽引、温熱療法などの物理療法、理学療法士によるマッサージやストレッチなど理学療法、神経ブロック注射(肩甲上ブロック、肩甲背ブロックなど)を行います。これらの治療でも疼痛が改善しない場合は手術目的で脊椎専門医の在籍する病院へ紹介しております。
狭窄の原因が椎間板ヘルニアの場合は自然と縮小、消退することが多く、疼痛が強い場合でも徐々に軽減し内服薬も減量、終了できる場合が多いです。頚椎症が原因の場合は一度生じた骨棘が消失することはありませんが、一過性の神経障害や神経周囲の炎症が消退すれば痛み、しびれは軽減、消失することも多く、手術が必要となるケースはごく稀です。
狭窄の原因が椎間板ヘルニアの場合は自然と縮小、消退することが多く、疼痛が強い場合でも徐々に軽減し内服薬も減量、終了できる場合が多いです。頚椎症が原因の場合は一度生じた骨棘が消失することはありませんが、一過性の神経障害や神経周囲の炎症が消退すれば痛み、しびれは軽減、消失することも多く、手術が必要となるケースはごく稀です。
頚椎症性脊髄症
原因・病態
頚椎の後方の脊髄の通り道を脊柱管と呼びます。脊柱管は前方は椎間板や後縦靭帯、後方は黄色靱帯、側方は椎間関節など骨、関節に囲まれたトンネルのような構造をしており、これらの組織が変形することで脊髄が圧迫され神経麻痺を発症した状態を指します。多くは脊柱管の狭窄のみでは麻痺症状が生じることはなく、それに加え頸の前後屈動作に伴う頚椎の前後のぐらつき(不安定性)や軽微な外傷がきっかけとなって発症することが多いです。特に日本人は欧米に比べ脊柱管が生まれつき狭いことが多く、本性を発症する割合が多いと言われています。
症状
四肢のしびれから始まり、進行すると筋力低下、手先の細かい動きの障害(巧緻運動障害:箸が使えない、字が書けない、ボタンかけが難しい、ものをよく落とす)や歩きにくさ(痙性歩行、失調性歩行:ふらつき、歩幅が小さく、歩くのがゆっくりとなる、つまずきやすくなる)、尿、便の出にくさといった膀胱直腸障害が出現します。
検査・診断
問診、診察で上記のような症状の有無、程度、上下肢の腱反射亢進がないかを確認し脊髄の障害部位がおおよそ推定されます。
検査では、X線(レントゲン)検査で頚椎の変形所見を確認します。変形所見には椎間板の扁平化(椎間板腔狭小化)、椎体の変形(骨棘形成)、椎体の前後のずれ(辷り)などが挙げられます。さらにMRI検査を行うことで脊髄の狭窄の強さを詳しく評価することが可能です。また、脊髄の障害が強い場合は脊髄内に浮腫像が描出される場合もあります。
検査では、X線(レントゲン)検査で頚椎の変形所見を確認します。変形所見には椎間板の扁平化(椎間板腔狭小化)、椎体の変形(骨棘形成)、椎体の前後のずれ(辷り)などが挙げられます。さらにMRI検査を行うことで脊髄の狭窄の強さを詳しく評価することが可能です。また、脊髄の障害が強い場合は脊髄内に浮腫像が描出される場合もあります。
治療
軽症例は薬物療法や装具療法(カラーなどによる頚椎の固定)、頚椎牽引、温熱療法などの物理療法、ストレッチ、筋力訓練などの理学療法といった保存的加療が行われます。重症例に対しては、保存的加療の効果に乏しく、そのまま放置するとさらに病状が進行するため手術加療が選択されます。
当院での診療内容
当院では薬物療法や物理、理学療法などのリハビリテーションを主に行っております。重症例や症状が進行する場合は早めに手術目的で脊椎専門医の在籍する病院へ紹介しております。術後も薬物療法やリハビリテーションが必要となる場合が多く、紹介先の病院とも連携を取りながら継続加療を行います。